![]()
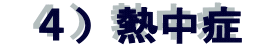 |
| ①体温調節のメカニズム |
| 2016/08/12掲示・2016/08/15更新 我孫子山の会ホームページ係(T・K) |
 |
 |
| 今年も熱中症の季節が巡ってきました。2回に分けて熱中症heat stroke/heat illness を取り上げます。 まず1回目では、体温維持の生理的な意味(なぜ体温は一定に保たれなければならないのか)、そのために人体が備えている体温調節メカニズムはどういうものなのか、とくに登山などのように持続的に、長時間にわたり体温上昇をきたしやすい運動では水分の十分な補給が絶対的に必要であることなど、体温の維持ということを中心のテーマとして解説していきます。 2回目では、体温調節の機構に破綻が生じた結果としての熱中症の病態と特徴的な症状、その防止策や、発症時の対応を取り上げます。 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|
| 【キーワード】 見方:キーワードが2か所以上ある用語は、2回目以降は( )に入れて示しました。 |
| 汗 汗による塩分の喪失 飲水量(必要飲水量) 環境温度 気化熱(2 3) 基礎代謝率(2) 恒温動物(2) 抗利尿ホルモン 水分の補給 代謝 体温調節機構 脱水 脱水症 脱水量 凍傷 乳酸 尿の濃さ(2) 尿量 熱中症 熱の放出 喉の渇き 排尿頻度(2) 排尿量 発汗(2) 皮膚温 皮膚血管反応 表層温 むくみ |
| 【キーポイント】 |
| 1)恒温動物であるヒトの体温は一定に保たれなければならない重大なわけがある。 2)人体が備えている体温調節のメカニズムでは、皮膚血管による反応(血管の収縮・弛緩)が第一に働き、寒さと暑さに備えた役割をしている。 3)高い環境温度下で運動をする場合には、汗の水分蒸発(気化熱)が最終的な体温低下の手段となる。 4)体内の水分は発汗によって多量に失われる。その際、塩分も失われるため、真水だけだなく、塩分も補給する必要がある。 5)体内の水分が失われると脱水状態(脱水症)をきたす。 6)脱水状態(+電解質の喪失)、うつ熱(熱の蓄積)状態の持続・亢進に体が反応しきれなかったときには熱中症を発症する。 7)脱水状態を観察するには幾通りかの方法がある。その1つが、尿量、尿の濃さ、排尿の頻度から推測する方法である。ほかには、自分の体重と歩行時間から推計する方法がある。 8)水は塩分・糖分などを含んだスポーツ飲料が体内(消化管)での吸収速度が速く、塩分(電解質)の補給もできるので適している。 9)登山での水の補給量は、飲みたいという個人の欲求よりもかなり多めとすることが適切である。 |
――なぜ体温は高くてはならないのか 変温動物も恒温動物も、代謝(生体のつくり変え・生命活動にかかわる化学反応で、異化と同化から成る)を行って、それぞれの生体の構造と働きを維持しています。触媒としてこの代謝を担うのが酵素です。生命活動は非常に多種多様で複雑な生化学反応*で成り立っており、各代謝にはそれぞれ種類の違う特定の酵素が関与していますが、これらの酵素類には、狭い範囲の至適温度があって、その温度域でしか十分に働きが行われません。
このように、とくにヒト(人間)をはじめとする各種の恒温動物では、体温(▼次のコラム参照)が一定に維持されなければならない重要な理由があります。そのために、恒温動物にはその目的に沿った体温調節装置(体温調節機能)が備わっています。
専門書によれば、種々の恒温動物はそれぞれ固有の体温を維持するようにできていますが、ヒト(人間)を除くこれらの動物たちも、極低温(非常に低い温度)と極高温(非常に高い温度)にさらされると、環境温度に影響されてしまい、恒温域からの「ずれ」(脱落)を示します。例えば、小鳥類(スズメなど)はほぼ40℃(超)の恒温を維持していますが、環境温度が30℃以上などと高温になると、外部の影響を受けて上昇し始めます。一方、大型の恒温動物のウシやウマなども、環境温度に影響されます。これらの恒温動物たちには、一定の範囲から外れると温度域に対して自己調節機能が備わっていないのです。 その中にあって、ヒトのみが外部の環境温度の激しい変化にもかかわらず、一定の体温(36~37℃)を維持することができます。ヒトにあっては、環境温度が低い場合には、衣類を着用すれば体温の低下は理論的にはいくらでも防ぐことができます。他方、環境温度が40~50℃と非常に高くなった場合にも、ヒトには温度を一定に調節する特殊な機能が備わっています。ヒトでは瞬間的には100℃以上の高い環境温度にさえ耐えられるといわれます。 特殊な実例として「サウナ風呂」がありますね。風呂内は50℃以上~100℃ほどと高温になっていますが、数分~数十分間はそれに耐えることができます。それが、発汗による体温調節のメカニズムのおかげなのです。この場合の発汗は、発汗の水分蒸発による熱の脱失とともに、生体表面をおおう汗の湿潤膜による高熱の伝達のブロック機能にあります(以下ではこの件は取り上げません)。
熱中症は、生体の種々の体温維持~調節のメカニズムが動員されて体温の維持が図られるにもかかわらず、それに逆らって種々の要因によって体温が高く推移してしまった結果として異常を生じる病態です(図1)。ヒトで環境温度が高くなった場合に最終的に温度調節にかかわるのが汗(しかもその蒸発の気化熱による)であるため、汗の源としての体液内の水分が減少した状態すなわち脱水症や、汗の蒸発が起こりにくい高湿度環境や不適切な人工環境(衣類や室温など)は熱中症の重要な引きがねとなります。 2回目で詳しく見ていきますが、重篤化した場合の熱中症の最終病態としては、体温中枢が機能しなくなって高熱を発し、意識障害、さらにショック*状態から死に至ることがあります。 *ショック:体の各臓器への血流が不足する全身性の循環不全。 体温の上昇は、①代謝の亢進*~運動強度の高まり、または②外界の気温(外気温;環境温度)の上昇――主にこの2つによって起こります。体温上昇に対しては、体温調節中枢のある視床下部からの自律神経作用を介して体温調節が行われます。 なお、体温の上昇はホルモンバランスの異常(バセドウ病など)や、病原菌感染による炎症などによってももたらされます。
人(ヒト)では、皮膚表面からの熱の放出によって体温調節が行われます。そのために高くなった核心温や、筋肉・臓器で作られる熱を血流(血液循環)によって皮膚表面により多く移動させる仕組みが働きます。 1)体表面からの熱の発散 ◆体熱放出の生理 通常、皮膚表面(表皮)からは、たえず熱の放出(放散)が起こっています。体表面からの熱の放出は水分の蒸発、伝導*、放射(輻射)**、対流***によって行われます。熱の放出は環境中に対して起こるので、環境温度が高くなるにつれて起こりにくくなります。体温と等しくなった時点で伝導、対流は完全に働かなくなり、さらに環境温度が体温よりも高くなったときには、逆に環境温度から熱をもらって体温が上昇し始めることになります。この段階では水分の蒸発、すなわち汗の水分蒸発だけが体温を下げる手段となります(図2)。 *伝導:物と物とが接しているときに、より高いほうから低いほうにじかに温度が伝わっていく現象。 **放射:熱の放射は赤外線で起こります。例えば、冷えた体の局所に温かい手を近づけると、熱を感じます。これは赤外線によるもので、真空中をも伝わります。「手かざし」などと呼ばれている民間療法は、この熱線を使ったものです。 ***対流:流体中の温かい部分と冷たい部分とが拡散(分子の活動による移動)によって等しくなろうとする現象。 他の動物たちが環境温度が体温よりも高い40℃などになると、環境温度に引きずられる形で体温が上昇するのは、動物たちが発汗作用を持たないためなのです。一般に動物たちが体温範囲(恒温域)を高めに持っているのはそのためで、体温が高ければそれだけ外部の高温の影響を受ける限界点を高くできるからです。逆に、高い体温は低温環境中では外部との温度差の大きさから、熱の脱出・喪失がそれだけ大きく、速く起こるというデメリットになります。動物の備える高体温による恒温維持というメカニズムは、両刃の剣といえますね。 なお、皮膚にある温度受容器が環境温度を感知して、皮膚・表皮⇒神経系⇒脳⇒神経系・ホルモン⇒反応・・の順序で起きる反応は、小さい動物ほどわずかの環境温度の変化で速く起こっているそうです。これは、小動物ほど環境温度に左右されやすい(環境温度がより速く深部体温に達しやすい)ため、体温低下予防から起きる当然の対応です。寒さが感知されたときには、動物たちは呼吸数・拍動が増えて発熱が促され、また毛や羽毛を逆立てたりして保温行動を示します。 上で、寒さに順応すると基礎代謝量が低下すると書きましたが、そうであるなら冬季には食事量は減ると考えられるでしょう。私は自宅でジュウシマツを20羽ほど飼っていますが、その逆で、冬では餌の量が明らかに多くなります。基礎代謝はあくまで基礎代謝であって、実際の生活にあたって活動する場合には別途の理解が成り立つように察しています。 ◆環境温度と体温の関係 体表面からの体熱の放出は、環境温度と自身の体温との温度差が大きいほど、つまり環境温度が低いほど起こりやすくなります(上に述べた動物の高体温では、核心温から皮膚温までの移行~伝達による熱の喪失の割合と速さはヒトよりもさらに大きい)。日常的な経験からしても、外気温が低いときに、さらに進んで「寒い」と感じるのは、体熱の損失が起こっているからです。「冷たい」いうのと「寒い」という感覚とは若干異なります。外気温を体の一部の温度受容器で感知すると「冷たい」と感じ、体全体に侵襲ストレスとして感じたときには「寒い」という感覚となります。寒いときに衣服を重ね着すると寒さが緩和されるのは、衣類によって体表面から熱が逃げるのがブロックされるからです。 一方、環境温度がしだいに上がってくると、熱の放出が起こりにくくなり、「暑い」と感じます。ただでさえ食事から得るエネルギーの大半(80%)が熱になるし、それ以上に外気温が高い環境中で激しい運動を持続させたりなどすると、体熱の産生は大きくなる一方なのに対して、その熱が外部に放出できないため、どんどん熱が体に蓄積される「うつ熱」状態となっていきます。体は強制的に熱を外部に放出しないと、体温が上がってしまい、危険です。人工的(もしくは能動的)な冷却(扇風機やエアコン、濡れタオル)で体温が下げられなければ、そこで発汗が発動されます。発汗によってもうつ熱傾向が続く場合には、運動を持続させることが生理的にできなくなります。 例えば登山中、あるいはランニング中に暑さから、運動強度を下げなければ、それ以上運動を続けられない状態というのがあります。息が上がる、非常に苦しいといったことを、みなさんも経験していることでしょう。運動強度が大きいと、おおよそ乳酸が多量に蓄積します。筋肉細胞にある乳酸は「疲労物質」とも呼ばれ、乳酸は筋肉細胞からいったん出て肝臓に運ばれて、酵素(乳酸脱水素酵素)によってピルビン酸に転換(還元)されなければなりません。乳酸は酸性物質であるため、蓄積すると筋肉を酸性にし、さらにATP(アデノシン三リン酸)の産生を低下させて筋肉運動を阻害するからです。瞬発性の運動強度(無酸素性運動強度)が高いと乳酸の代謝速度が産生速度に追いつかず、筋肉にたまっていきます。運動強度が高くない、いわゆる有酸素性の運動レベルであるなら、乳酸は過剰には作られないし、ピルビン酸への転換も起こりやすいのですが、体温が高くなるとその転換も起こりにくくなります。激しい運動が持続できなくなる理由です。
2)皮膚表面からの体温放出 体温低下を促進するメカニズムにおいても、最初から機能全部の一挙動員がなされるのではなく、過剰反応にならないように程度に応じた調節順序がとられます。体温低下にかかわる機構から大きく分けると、①表皮(体表面)からの直接的な体温放出と、②発汗による体温放出に分けられ、①で体温調節が厳しくなった段階で②が本格的に発動されます(ただし発汗は軽微な段階から絶えず起こってはいます)。 まず最初に体温を低下させるように働くのは、皮膚表面近くに分布する血管(表在血管)です。皮膚表面に多量に血液(動脈血)が流れやすくするために、表在血管の拡張が最初に起こります。逆に寒いときには、血管が収縮して血流減少を促すように反応します。このような、外気温の上がり下がりに対応して起こる、体温調節にかかわる表在血管の動きを皮膚血管反応といいます。これらの反応は、自律神経系の神経調節と、ホルモン調節によって担われています。寒さ・暑さはストレスとして生体は感知しますが、そのほかの種々のストレスに対しても、カテコールアミンという副腎髄質ホルモンの1つであるアドレナリンadorenaline (エピネフリンともいいます)を介して対応を行っています。神経系は、その上位で調節を統合します。 血管は心臓に戻っていく静脈系と心臓から送り出される動脈系に大別されますが、外気温が低いときと高いときとで、体温調節を次のように行っています(図3)。 (1) 外気温が低いとき:温度差が大きいほど熱の放出が大きくなるので、表在血管を収縮させて、表面の温度を低くする皮膚血管反応が起きます。それでも体温低下が防げないときは、人工的な保温措置(衣類・手袋の着用、暖房など)をとるしかありません。 (2) 外気温が高いとき:血管が拡張して、皮膚への血液循環を促し、皮膚からの体温放出を増加させるとともに、汗腺(エクリン腺)への血流を多くして発汗を促します。体温低下は最終的には汗の水分蒸発による気化熱の冷却効果に依存します(図4)。 血流が増すことによって表皮の温度を上げ、皮膚表面からの発汗と蒸発も起こりやすくなります。気化(蒸発)の起こりやすさは外気(環境)中の湿度に依存しているため、湿度が高い環境にいると熱中症は起こりやすくなります。
3)1日の最低水分摂取(飲水)必要量 人体からの水分の蒸発は発汗として出るものばかりではなく、呼吸や非発汗性の水分蒸発としても起こり、これを不感蒸泄(不感蒸散)といいます。1日に、肺から呼吸によって0.4L、皮膚からも安静状態で0.6L、合わせて約1Lの水が体内から失われています。 それ以外に、通常で代謝に伴う老廃物の排泄に尿として1L程度が外部に出ていきます。腎・尿路系は、人体が代謝を行って不要となった代謝産物を体外に排泄するのに、いらなくなった物質をそこに溶かし込んで捨てる経路~溶媒となる機構ですが、それらの物質が溶ける濃度は一定の範囲までであるため、老廃物を溶かし込むに足る水分量が最低でも必要になりります。この尿を不可避尿といいます。 以上から、なにもしなくても不感蒸散と不可避尿だけで、1日に1.5~2Lが体内から失われていきます。 一方、栄養素の代謝によって代謝水が体の中で生じています。例えば糖質(炭水化物)が完全に代謝されると、水と二酸化炭素(炭酸ガス)にまで分解されますが、その水が代謝水となります。100gの炭水化物が完全燃焼すると55gの代謝水が生まれます。脂肪では107gです(文献4)。一般に代謝水は日常の食事で1日に約0.3L作られます。これらの水も含めて、普通の成人における水の出入りは図5に示されるようになっています(文献によってやや値が異なります)。 なお、甘い物(代表は砂糖)を食べると喉が渇くということが言われるのを聞いたことはありませんか。しかし、甘い物を食べたからといって、体液を濃くするような物質はなんら産生されません。二酸化炭素は肺から呼吸によって出され、代謝水は体内をめぐり、尿となります。タンパク質も脂質(脂肪)も代謝されると水を生じます。わずかですが、0.3Lの代謝水も水の足しとなっています。
登山で水をどれくらい持てばよいか、といった質問を投げかける人がいますが、1.5Lという量は割り引いて考えても最低量です。ほしいだけの水ではなく、必要な量を積極的に自分に与えましょう。 参考【山本氏方式】 山本正嘉氏(鹿屋体育大学教授)によると、脱水量は次の計算式で求められます(文献3)。著者自身が登山家でもあり、また被験者に同行してもらい、求めた式だそうで、ザックの重さや季節、山の高さは違ってもあまりバラつきなく当てはまる式のようです。 脱水量〔g〕=5〔g〕×体重〔kg〕×歩行時間〔h〕 また、脱水による障害を予防するには、脱水量だけ補給するのがよいとしても、水は一番重い装備だから十分量持つことは大変です。そこで山本氏が推奨するのが、脱水量が体重の2%以下までにに抑えるように飲水する、というものです。体重が60kgの人が8時間の登山をする場合には、2400g(2.4L)になります。一般に、上記の脱水量をAとすると、飲水量は次の式で与えられます。 飲水量〔g〕=A-20×体重〔kg〕 となります。体重60kg=60000gから、その2%は1200gなので、体重60kgの人が8時間の登山をする場合には1200g(0.6L)の水を補給すればよいことになります。ただし、脱水が体重の2%というのは、正常な生理現象が維持できるぎりぎりの線をいっています。さらに尿、呼気でも失われるので、これらの水分も入れて脱水の総量は考慮すべきではないかと思われます。 ※注)私は上記の山本氏の計算式に疑問点を抱いています。パラメーター(要素)に気温が入っておらず、ザックの重さも、標高差も勘案されていないからです。これについて少しふれておきます。 脱水には、主に発汗(発汗量)がかかわります(高所の登山では呼吸も脱水に関与しますが)。発汗は、上で詳しく見てきたように、体温を下げる目的で行われるものです。体温の産生を行うのは、主に運動に携わる下肢や体幹の筋肉、そして肝臓、さらに呼吸筋です。発汗は外気温との差が小さくなった場合、すなわち外気温が高くなった場合に顕著になるということを書きました。そのほか、発汗は産生する熱量、つまり運動の強度、エネルギー消費を反映しますから、自重だけでなくザックの重さや、標高差・傾斜も関係してこざるをえません。なるほど、傾斜が急になると歩速はゆっくりとなるため、時間がそれだけ長くかかります。歩行時間は傾斜の程度(平均斜度)と標高差にも左右されるので、これらは歩行時間にまとめて示されるかもしれませんが、運動強度は仕事量(エネルギー消費量)は「(持ち上げる)高さ×質量(重さ)」なので、ザックの重さをパラメーターに加えなければいけないはずです。ザックが重いとそれだけゆっくりとしか歩けないため、歩行時間に長く反映されるので、時間の長さで代表させると考えるのかもしれませんが、体重だけが勘案されているのは合点がいきません。 あるウェブサイトによると、登山におけるエネルギー消費量の算出に、平均のおおよその斜度やザックの重さ、さらに年齢なども勘案しています。年齢を考慮するのは、年をとるほど無理がきかなくなる、すなわち自然に歩速が落ちるから、それだけ時間がかかるためと理解されます。
上に述べたように、運動などをしないで、ごく普通の生活をしているだけで、1L+1L=2Lの水が体から失われていくのです。このことをきちんと認識しておきましょう。運動をする場合には、それ以外に数L~10Lという水が体から汗として外に出ていきます。汗の量は運動強度、持続時間、環境温度などで変わってきますが、少なくとも数Lとなることは確実ですし、10L(1時間に2L)にも及ぶことがあるそうです。 ◆尿による適性水分量の目安 運動強度は本人の苦しさや負荷の自覚から主観的にとらえることができますが、別の側面に視点を当てて、発汗量に対して水分量が適正かどうかを逆に客観的に観察する方法として見てみましょう。繰り返しになりますが、排尿の頻度および尿の濃さを指標とするものです。 ①尿量、排尿の頻度:上で述べた代謝に伴う水分排泄機構としての尿の分量を1Lとしましたが、これは生理的な(つまり健康を維持する最少の水分量だという意味における)量であって、飲水量や食事の内容、生活スタイル(仕事の種類)、運動の有無などによって大きく変わってくることは上で述べてきたとおりです。登山では急激に体の水分が失われ、水分の適正な補給が行われなかった場合には、ADH(抗利尿ホルモン)の分泌によって尿量の減少をきたします。体内の水分が不足してくると、尿量の減少という現象が明らかとなります。通常の生活では1日の尿量は1500mL程度とされます。また尿量は1回あたりの尿量とともに、排尿回数もその指標になります。普通の生活では朝~夕方の間に4~5回の回数として、登山中に何回それを行ったか自己観察を欠かさないようにしましょう。 ②尿の濃さ:尿の濃縮(一定の水分にどれくらいの老廃物を溶かし込んで尿が生成されるかという機能で、その尺度を尿の濃縮能と呼びます)には限界があります(ちなみに、塩分の摂取量とも関係しますが、一般に尿の塩分濃度は0.8~1.2%の範囲です)。登山においては、通常の濃さと比較してどうか、ということを色調から観察します。濃すぎる(褐色調の)尿は水分不足を示しています。排尿の頻度とあわせて観察し、2時間程度に1回、黄褐色の薄い色調となる程度まで水分を補給する必要があります。 上のコラムでも述べましたが、脱水状態がある臨界点(この閾値を私は知りません)を超えた場合に自律神経支配によりADHが出されてしまうと、そこで尿の強制的な濃縮が開始されるため、尿量が減り、排尿の回数も減ります。こうなっては手遅れなのかもしれません。ADHは一度分泌されてしまうと、数日間血中に高くとどまるといいますから。 4)汗(発汗) 汗はエクリン腺から分泌され、小じわを伝わって広がり、蒸発を促す構造になっています。また、図3に注記しましたが、汗は体表面にとどまって蒸発して初めて効果を発揮します。体毛はエクリン腺のそばに分布しており、汗の流下を防ぎ、蒸発に役立っています。 汗には0.3~0.8%の溶質(主に塩化ナトリウム;塩=ナトリウムイオンNa+と塩化物イオンCl-)を含んでいます。血漿(血液)の塩分濃度は0.9%(水1Lに食塩約9.1gが溶けた濃度で、生理食塩水が同じ)なので、それより薄いですが、とはいえ、発汗によって塩分も同時に失われていきます。 【参考】手のひら、足の裏側は他の体表面の発汗と異なった神経支配を受けています。手のひらの汗は自律神経のうち交感神経の支配を受けています。この部分の発汗は、例えばサルが木の枝を移動する場合を想像しても、またヒト(人類)がそもそも動物たちとの生死を賭した闘い(狩猟)に必要だっただろうことを考えても、戦闘モードに備えた発汗だと考えられます。その戦闘モードにおいては、体表面の発汗などは不急の備えなのでしょう、他の体表面の発汗は、「ほっとした」状態で優位となる副交感神経の支配を受けています。サッカー選手や短距離走の競技中には、皮膚表面は発汗せず、競技が終わったときや、競技中でも立ち止まったときに発汗は起こるそうです。ところで登山では、始終、発汗が起こっていますが、これは、登山が精神的にずっとほっとしながら行う活動であることを示しているのかもしれません。 交感神経によって皮膚表面に発汗を起こさせる精神性発汗というのもあります。 ◆体液と発汗による水・塩分の喪失 ここで大切な点を書き添えます。 上のコラムでも書きましたが、汗(発汗)によって体から水が失われるのに伴って、少なからず塩分も失われるということです。2回目で述べますが、熱中症のうちで熱けいれんというのは、塩分喪失からおこります。水だけを補った場合に、体液濃度の低下(電解質減少)によるものです。 例えば、体重70kgの人が炎天下に10分間いるだけで体温が1℃上昇するそうですが、人体の熱容量(比熱)を水と同等として、このときの必要発汗量を計算してみると、体表面での自然放熱効果も含めると、100g(100mL)の汗が蒸発すれば、この体温上昇分をほぼ抑えることができるとされます(100×0.58=58kcalなので、70kg全部を発汗だけで1℃下げるには、少し足りません;下記の文献2から)。 このときの汗の塩分濃度(0.3~0.8%)の中間値をとって0.5%だったとしましょう。100g(100mL)発汗したとして、約0.5gの塩分が体外に持ち去られる勘定になります。これに運動負荷の程度と時間を掛けてみましょう。その10倍の5gが体外に出るのに、さほど時間はいらないことがわかります。1日の日本人の食事からの塩分摂取料は10~15gほどですが、その程度の塩分は1日の登山で簡単に失われていくことがわかります。登山など運動強度がある程度高く、かつ長時間続く場合には、塩分を補ってやる必要があります。 とくに激しい運動でない場合や、短時間の運動(日帰りの登山)などでは、食事から相当量の塩分が摂取できているので、塩分摂取に関して格別の注意は必要ないともいわれていますが、重登山(長時間~数日の縦走登山)では、食事量も減り、逆に排尿状態から観察し、できるだけ日常と同じの尿の濃さ、排尿の頻度に近づけるように水分摂取に努めることが重要です。 ◆水分の補給 スポーツ飲料の代表格である「ポカリスエット」は、飲料水で100mLに0.12gの塩分を含んでいます(0.12%の濃度;▼オオツカ製薬ネット情報)。体液よりもかなり低く、汗の塩分濃度よりも薄くなっていますが、塩分を補給するには適しています。一般にスポーツ飲料には主に糖分と塩分、ビタミン類などが含まれていますが、これらの成分が溶解することによって、小腸の腸管での浸透圧差ができて水が速く吸収されるのだそうです。真水と比べて吸収速度は20倍以上に速くなるとされます。スポーツ飲料がない場合には、食塩と砂糖を水に溶かして便宜的に作ることができます。激しい下痢(脱水を起こす)を伴う感染症なども、こういった経口補水液の適応となります。 なお、登山が激しい運動だといっても、通常、登山が1~2時間経過すると発汗量はしだいに減っていきます。通常、粉末のスポーツ飲料をメーカー推奨の量の1/2~1/3量、定量(1L)の水に薄めに溶かした飲料水が勧められます。それらを含めて、おのおのの好みの飲料水(お茶、コーヒーは利尿作用があるので控えめに)を多めに飲むようにしましょう。 登山における飲水量に関しては、興味ある研究結果があります。登山をするグループ(同一年代、同一性)のメンバーを3つのグループに分けて登山をし、それぞれ異なる水分摂取をしてもらった結果からです。文献4も同様な結果を報告しています。 第1グループ:理論的な必要量(これだけと決めた量)を飲んでもらった 第2グループ:個々で飲みたいと思った分量だけ飲んでもらった 第3グループ:個々の欲求とは別に、それ以上に強制的に多く飲んでもらった 以上のグループの中では、第3のグループが脱水が最も防止でき、体温上昇もきたさずに体調よく登山が行えたとの報告があります。短時間の登山では、体の中の水分がかかわる機能などに明らかな変化は現れないかもしれませんが、それを健康状態のデータから見る限り、健常な状態は「(欲求とは関係せず)無理してでも水は多めに飲む」ことによって維持できることを示していると思います。 以上から、脱水症では人体というものは意外と飢餓感や口渇などの感覚としての大ききや緊急度をそのまま示さない(実態よりずっと控え目な欲求度しか示さない)代わりに、自身はちゃっかり早めの内的な処理(ADH分泌による蓄水)を施し、生き延びる方向に勝手に模索しており、だから多少の無自覚で粗末な態度でも、異常を起こさないで安全の範囲を保っていられる、ということがいえそうですね。とはいえ、それは人体が利口だからなのであって、それに頼りきりというのは生体という自然に依存しすぎていますし、現代人としては自覚を欠いていないでしょうか。 単なる水ですが、なかなかにして奥の深いものがあります。(2回目に続きます) ●参考文献 このページを書くに当たっては、次の文献を参考にしました。 1)三輪一智・中恵一著:生化学(系統看護学講座・専門基礎―人体の構造と機能2)、第13版、医学書院、2014. 2)本間研一ほか編:標準生理学、第14編・第2章「体温とその調節」、第8版、医学書院、2014. 3)日本登山医学研究会編:登山の医学ハンドブック、第2版、杏林書院、2002. 4)山本正嘉著:登山の運動生理学百科、東京新聞出版局、2000. 5)日本山岳会医療委員会編:山の救急医療ハンドブック、山と溪谷社、2005. 6)J.A.ウィルカーソン編/東大スキー山岳部医学部OB訳:登山の医学、東京新聞出版局、1982. |
