![]()
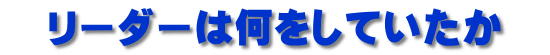
| (本多勝一著、朝日新聞社〈朝日文庫〉、1997年初版) |
 |
 |
 |
| 本多氏の山関係の著作物は少 なくない。 |
著作物の一部。関心領域は多方面にわたる。 |
|
| ずいぶん前に一度読んでいたが、最近、本会で山岳遭難の防止の課題が大きく取り上げられるようになったこともあり、ちょうどいい機会と思い、読み直してみたのが本書である。教訓に満ちた内容であり、多くの山好きの方たちに一読してほしい作品である。『山を考える』も示唆に富んだ1冊だ。 ■者のプロフィール 著者の本多勝一氏は、知る人ぞ知る、朝日新聞社の名物記者であり、新聞記者畑を一貫して歩いてきた方である。新聞記者としては異例に、朝日文庫版として30冊以上のタイトルで個人の作品を出版しているが、ほかに他の出版社からも多数の著作や、山岳雑誌での紀行文、対談、座談がある。 長野県飯田市(著者の表現では「伊那谷」)の出身で、中央アルプスを間近にしたという地理的な影響も少なくなかったのだろう、飯田高校時代からたびたび中央アルプスの登山を行い、とくに南駒ケ岳には好んで登ったという。その後、京都大学時代には山岳部・探検部に在籍し、卒業後はヒマラヤにも足しげく通ったようである。その経歴からも、登山に関する著作は少なくない。そのうち、あるころから山岳遭難にかかわる事例を追跡し続けてきたようで、本書はその範疇の作品だ。 とはいえ、山ばかりにとどまらず、ポル・ポト時代のカンボジアの悲惨な内戦、東西冷戦の中でのアメリカによる南ベトナム傀儡政権の樹立に始まるベトナム戦争、あるいは歴史をさかのぼって日本軍による中国の侵略(南京事件や、日中戦争、中国・満州の侵略などに関して、中国各地を歩いて生存者の声や、遺構・遺物などに基づき史実を探った)など、戦中・戦後史においてショッキングな出来事を扱ったタイトルが並ぶ。かというと、対象をまったく替えて、冒険にまつわる特異的な視点でのアムンゼン・スコットの冒険考などと、多彩な方面から出版活動を展開してきた。 また、伝統ある京都学派・今西錦司の門下で、その独自の自然学(ナチュラリズム)の系譜を引くだけあって、その論考の自然科学者的な組み立て、展開の緻密さはさすがと思わせる。 ■本書の概観と著者の姿勢 本書は360ページ程度の文庫本だ。最初に「山岳遭難と報道の戦後50年」と題して、山岳雑誌『山と溪谷』編集長(当時)の神長幹雄氏との対談を載せている。そこで、戦後50年の間に起こった山岳遭難の推移を概観し、どこが問題かを論じている。遭難が多発した背景には、時代的な要因があった。日本経済の成長とともに多くの若者が故郷を後にし、その成長を支えた。急速に改善した生活環境が登山熱を刺激し、多数の若者が山に向かった。今では珍しいが、多くの高校に山岳部が置かれた。 しかし、それは登山の危険を、経験・技術習熟度において未熟な世代に身近に引き寄せさせることとなる。山岳遭難事故が若者を中心とする登山者に頻出するようになった。当然のごとくして、わが子や家族が遭遇した山岳遭難という「被害」に対して、実施主体の責任を問う風潮が出始めていく。裁判沙汰に事態は及んだ。最初の事例となったのが、1967年の朝日連峰での山形市立商業高校山岳部3人の疲労凍死事故に関する裁判だった。山岳部顧問の責任が問われたが、遭難(危険)の予見可能性(⇒登山における「注意義務」試論(2)中―7-4)参照)が否定され、無罪となった。この事例では、実況的証拠の立証が難しく、「被害者」は泣き寝入りすることとなる。しかし、その後の裁判事例を通して、山岳遭難が人為的な要因によって引き起こされていることが立証された。著者は「被害者」側の証人として何度も出廷している。この立証に、本多氏の記者魂がもたらした影響は小さくなかったと思われる。 ところで、著者はとくに記者としての鋭い視点を保持しながらも、市井の常識人として、遭難事故に込められた社会的な責任論を展開して、一般読者としてわかりやすい理解に到達できるよう配慮している。しかも、山の「常識」を高いレベルで体得している著者ならではの証言の豊かさや科学性に加えて、平易に語る言葉の力を併せ持っているうえに、さらにジャーナリストとしての資質を決定する正義感覚のバランスにも優れている。その著作に接して、著者の高い倫理観や正義感、あるいは弱者に対する精神を感じる。けっして高踏な理論をもてあそぶようなところはない。だから、著作の中身は抵抗感なく読め、非常に溶け込みやすい印象を与える。 また著者は、社会的、政治的な、またはどのような世界であれ、奇怪な、疑問と感じる問題、事象にぶつかったときには、人はいつも「常識」に戻って考え、判断し、行動するということの大切であることを、たえず読者に説くかのようである。新聞の論調がしばしばとる、高みに立ってになにかを説諭するといった姿勢は、本多氏にはない。 ■山岳遭難事故の実態 戦後、起こった大規模な山岳遭難事故として、1963年の愛知大学学生による薬師岳遭難(13人全員死亡)があげられることが多い。そのころを境として、とくに学生が主人公となる山岳遭難事故が繰り返される。著者はその前に起こった北海道での山岳遭難で、生き戻った者と死亡した者とにどのような理由や原因で区分けされるのか、そのことに疑問を抱き始めていた。亡くなった人の原因を探っていくと、現在は症状から「低体温症」といい、かつては「凍死(または疲労凍死)」という表現でいう死因が、下着(木綿)にあったことを突き止める(死を免れた1人だけ肌着がウールだった)。そして、それまで山での遭難(無償の行為)が美化される傾向があった世論に対して、いたずらな山での犠牲を繰り返さぬように新風を送る記事を書く。遭難を追跡していくと、無駄に山で逝った人たちがいることが明らかとなった。下着に原因があったのであれば、死ななくてすんだ事故だったということになる。それも、ある傾向を持った社会的な現象ともいえる、大きな「欠陥」や「危険」を伴った遭難事例に出くわす。 本書で取り上げられるのは、比較的今日に近い時代に起こったそのような類似の事例である(とはいえ本書は初版の出版からすでに17年も経過している)。いずれも、記者として現場に趣き、可能な限り状況を自身の眼で正確に把握する、すなわち間接的な情報では記事を書かないことを徹底して、遭難が起こった真実に近づこうとする姿勢を貫いている。遭難が起こった同じ時期に3000メートルの地点に足を運び、またときには空から現場を俯瞰もしている。徹底的に現場の状況を確認し、事故の再現性(同じ状況・条件下でそこに立った場合に高頻度で遭難が起こる可能性)を目で確かめる。 しかも、遭難事故であり、山で犠牲となった死者に対する著者の姿勢はあくまで慎み深く、遺族に対する哀悼を忘れるようなことはない。著者の「人柄」が行間に出る。上に「常識人」として、と述べたのは、著者自身が記者のにおいを漂わすことなく、普通の市井に生活する1人としての感覚・感情に基づいて、疑問を感じる事案には感じるままに接近し、また遺族の気持ちに寄り添いながら、自ら語ってくれるのを待つ忍耐、厚い情を持っているという意味においてである。私は本書を読みながら、著者の人間的なあり方に共鳴した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ さて、本書の中身であるが、取り上げているのは、1980年12月に起きた逗子開成高校山岳部の八方尾根遭難から始まり、77年3月の都立航空工業専門学校の中央アルプス・将棊頭山遭難、82年4月の関西大倉高校山岳部の八ケ岳遭難、78年4月の静岡県社会人体育文化協会の八ケ岳遭難、88年11月の前穂高岳北尾根のガイド登山遭難の5事例(配置順)である。最後のガイドを伴った遭難以外はすべて、山岳部顧問や学校の先生、あるいは団体の職員が付き添っており、端的にいえば、その「リーダー」「引率者」の間違った判断によって遭難が引き起こされたと論じる。その中には、その企画自体があまりにも無謀で、現在なら、そのような企画が公然となった時点で厳しい社会的な批判・非難を招くに違いないと思われるケースもある。 現在は私的な団体(公益社団法人日本山岳ガイド協会)による資格付けがあるが、登山での公的な資格付けは依然、わが国では行われていない。どういう資格が必要だとか、公けに問いただされることもない山登りであり、いきおい「無資格」の引率者が表面に躍り出ることがある。それにもかかわらず、それらを「有資格」と鵜呑みにする生徒たちとその親たちに対して「ガイド」のような立場に引率者が躍り出たとき、もしも登ろうとする山が危険をはらんでいたなら、結果がどうなるであろうか。 遭難を引き起こした事例はいずれも、わが国の山岳領域では高所を目標とし、しかも厳冬期の初期から残雪期の春山にあたる、厳しい時期に行われた登山ばかりである。その危険な山に、登山の無資格者(資格が問われないという意味とともに、経験・技術・知識がないという意味の両方で)が誘導または引率する登山である。著者はそれを、「運転免許を持たない運転手が運転するバス」にたとえる。しかも、引率される側も山の危険に関して認識を欠く。山登りに関する自律した判断力を持たない人たちであり、いわば、そそのかされやすく、だまされやすい人たちである。どちらからみても、その危険が最初からきわめて大きいことがわかる。 誰が読んでも、このような危険な時期に、可能性としておおいにありうるだろう危険を認識もせずに踏み出していく無謀な登山パーティーがあったということに、驚きとこわさを感じるのではなかろうか。実は、社会人よりも若者、とくに高校生や大学生が登山においては最も危険な世代(冒険への気概がある反面、自覚や安全への意識と実質の力とのアンバランスが大きい世代)だと私は考えているが、ただでさえ危険なそのような世代を預かる教師や山岳部顧問は、より厳しくその目を見開いて、「保護者」として若者を指導し、庇護しなけれならない立場にある。ところが、本書で扱っている事例は、「保護者」が危険への誘導者となってしまうのである。 では、こういうことがなぜ起きるのか。著者の推理するそのカラクリである。いずれのケースも、素人であれ「引率者」が「被引率者」の前に出たときから被引率者の目または認識に生じる、不安を打ち消す「権威」をまとう「仮面(表見)効果」から解き起こし、その社会心理を蓑としてまとった危険行為の虚構性を暴く。それが、「運転免許を持たない運転手」である。しかし、バスがやって来て、その運転手の資格や資質を乗車しようとする側が疑うなどということはなく、一種の権威への無前提の意識の導入が起こっていること、その装いをもって生徒・学生たちの前に「引率者」が立ち現れていることを立論する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎参加側の非はなかったか―「好意同乗」の観点からの私見 ちなみに、著者は言及していないが、私見を書き添える。子どもも親も、自身が、わが子が高所に向かっていこうとする気概を、不安に思う一方で誇らしくも思う気持ちを持たなかったかと、その動機を私は推測する。著者は、「虚構」の上に立って動機を引き出した主催者(教師や引率者)を一方的に批判するが、参加した側(学生とその親、または市民)における心理的な弱みはなかったのかも私は考えたい。参加ということの前に、自己肯定感に裏づけられた気持ちの高揚感が伴っただろうと推測する。高所に向かうというときには、いつもこの気持ちが支えとなっていることをそれぞれで思い返してほしい。この気持ちが裏腹の心理として介在したのではなかろうか。また、危険な行為は、一種のエリート意識をもはぐくむことがある。危険を冒すという刺激的な心理がいくばくかでも参加者の心理に潜り込んでいき、参加を選択させた面があるのではなかろうか。とくにその心理が起こるのが、完全な個人の自由な選択によった静岡体文協の八ケ岳事故や穂高岳のガイド登山である。 さらに、別のところで書いたが、いくつかのケースは「好意同乗」にあたる側面を持っていると思う(⇒「登山における『注意義務』試論②」の書き出し部分)。「好意同乗」では、見込める利益と同時に請け負うべき危険の意思があるはずである。ここで問題になるのが、「善意ある管理者の注意(善管注意)義務」がどうだったか、である。善管注意の程度は、引率者なら自身の子どもに対して払うだろう注意義務が基準になるのではなかろうか。わかりやすくいうと、自分の子どもに対して、本書であげられたような危険な登山に参加するように勧めるだろうか、という問いへの回答を実施者・引率者側に求めることになるだろう。 著者はそれには一切言及せず、逆に、その資質もない主催者側の行為にだけ疑問符を投げかけているが、その心理的な罠にも言及があってよいのではなかっただろうか。ただし、高校または大学の山岳部で起こした事例に関しては、これらは、いわば「閉鎖系」の中での半強制という面が非常に大きく作用したであろうことは、著者の説くとおりであろう。 以上から、さらに別の見方を加えれば、これらの遭難事故は、高校生の場合には、いわば「体制(組織)」内的な強制という力が働いていたのでややずれるが、その小さな「体制」を取り巻くより大きな社会的な監視ということの欠如、あるいは問題意識の社会的な共有という「文化」としての未熟さに根本的な原因があったと思わざるをえない。それに対して危険信号を発することもせず、制止もしなかった「社会意識」の低さという未熟さにこそ、第一の原因があったと感じる。その意味では、遭難回避という「新しい文化」の発現には、ある種の意識の喚起、文化の構築がなければならないし、その意識が多くの市民で共有されて制度として財産化されなければならない。その喚起を本多氏らのジャーナリストたちが引き受けたことの意義は大きいと思う。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ◎中身の紹介 中身はリアリティーをもって書かれている。1つ2つ紹介しておく。 1978年4月の静岡体文協の八ケ岳(横岳)遭難は、30人近い参加者で成る素人登山集団で起きた事故である。このツアー登山は、「まさか」と思わせるほどの非常識な、お粗末な内容だったようだ。半公的なと思われる名称の団体(ところが実は私的団体)で「公募」され、にわか作りのメンバー形成であり、人数の割には少ない「添乗員」がリーダー側として付いたが、参加者は隣人に配慮するというような関係を欠いていた。そのパーティーを率いる側(企画した側といったほうがよいかもしれない)も危険の認識がないまま、夜行バスで発って、早朝、一行は麦草峠から登山を開始した。なんとアイゼンもピッケルも持たず、もちろんザイルでの安全確保などはない(短いながらロープ1本だけはあったという)。延々歩き続けて黒百合平、天狗岳、夏沢峠、硫黄岳を過ぎ、横岳まで来てしまった。ご承知の方はその時期の、そのあたりの危険性が十分に想像できるだろう。すでに相当の距離を歩いているうえ、この経路の中では最も厳しく、危険度の高い場所である。ここを通過する際に、1人の若い女性が何百メートルも滑落して亡くなった。そこの状況を知る者にとっては、起きておかしくない遭難と感じるだろう。 横岳の通過では、数十メートル、西側(赤岳鉱泉側)に下って岩稜帯をトラバースする箇所がある。そこは、雪がついた時期だったら、われわれでもザイルを使うような危険地帯だ(⇒「ギャラリー」中の横岳)。事実、ここでは事故が何度も起きている。ところが、主催者側は本人の不注意によるものだと「自己責任」を主張した。これは、どう考えてもおかしいと家族が裁判に訴え出ることになる。著者は出廷して、この時期における横岳の通過に対する主催者側の認識(危険の予知・回避義務)の欠如、注意義務違反の責任を強く述べている。 最後のプロのガイド登山では、前穂高岳から鞍部(吊尾根)へ下り切る前の地点で、吊尾根をそのまま行かないで、いきなり岩稜帯から涸沢への下降を試みている。その結果、自ら雪崩を引き起こし、同行の男女2人が死亡している。そもそもこの時期に素人(2人の経歴から)を前穂高岳北尾根にガイドすることがありえただろうかという疑問もさることながら、その地点から涸沢への下降という、非常識な行路の選択が行われたことが決定的である。日照時間が短い時期であったにもかかわらず、3人が涸沢を出たのが午前7時半を過ぎていたようだから、すでにこの時点で、前穂高岳-奥穂高岳を経て涸沢に戻ってくるという計画にはほころびが生じていたのではないかと私は思う。それが、性急に危険な行路への変更をさせてしまったことになったのだろうと著者はいう。 雪がない時期はもちろん、雪の降りた岩場のあの傾斜を下るなどということは、素人でもしないだろうと、涸沢から吊尾根を眺めるたびに考える場所だ。これらの前提的な認識がどうであったかはともかく、「被害者」の2人はプロのガイドだからという信頼が先行して、迷うことなく追従した。事故はその結末だった。2人はガイドに「殺された」のではなかったかという思いは、本書を読んだ多くの人に湧くに違いない。 これらの例から、いずれも、度の過ぎた不合理な登山、そしてそれを引率する者の資質(資質のなさ)によって簡単に遭難が起こってしまい、同行者が無用に死に陥れられるという共通の構造を持ち、それを野放しにして、これ以上の犠牲者が出ることを阻止したい、との著者の気持ちが伝わってくる。 ■自己責任と事故回避の方法 本多氏の努力もひと役買った世論の喚起によって、山の危険は公知の事実となった。今日では、登山を行う者は登山という行為自体の持つ危険性をまず現実の与件として認識しなければならない。そこにおける自己責任意識を本人が確実に持つことからスタートすべきである。そして山岳会や集団での登山、またリーダー役を負った者においては、パーティーの構成員間での相互の関係からリーダーの落ち度に由来する事故が生じた場合には、リーダーの責任問題となることがありうるとの認識を欠かさないことが大切である。まずは行為者自身でその登山の危険性と責任を十分に自覚し、そのうえで隊として実際の登山は、隊員間での役割を正しく持って慎重に行うべきだということである。そして集団での相互の「経験・力量格差」が大きい場合には、状況を正確に見極めたうえで、登山は行うべきことが、登山界の今日の約束事となった感があるように思う。 弁護士の溝手康史氏の『登山の法律学』(山と溪谷社)でも、登山は自己責任を第一とする危険行為だという解釈から法律解説を展開している。登山とはどこまでも危険行為だとの本人の自覚を前提とすべきだというふうに私は読んだ。 戦後から30年そこそこのころと、その文化的な財産の共有がなされた現代とでは、状況は大きく異なると思う。現在では、遭難回避意識にかかわる「文化」はすでにゆきわたっており、危険の警報は、もはや聞かないほうに落ち度がある、危険への安易な転落は、その個人にこそその責任があると思う。かといって、「振り込め詐欺」の犠牲になる人が、声高く注意が喚起されているにもかかわらず、依然として絶えないし、山岳遭難とて今も同じように繰り返され、皮肉にも今昔の違いがない現象のようにも感じる。今日では、その主役が「中高年世代」に替わったといわれる。 ■山で起きうる、必然性のない事故 本書が扱っているような事例は、事故と原因との因果関係が大きいケースばかりである。ところが、そうではなく、事故の必然性や因果関係がないにもかかわらず、わずかのひずみによって、その場所の状況や時期、人の疲労度、天候的な条件などなどマイナスの要因がたまたま運悪く重なった場合に、簡単に事故は起こってしまうことを私も経験している。例えば、「浮き石」に運悪く体重を乗せる、つかんだ岩が外れたなど、普通にありうるアクシデントに、状況が合致してしまった場合、大事故につながる可能性がある。不可抗力といえる偶然のなせる結果だ。それらの偶然に、どう対応したらよいのだろうか。その疑問が脳裏から去らない。 以来、山での絶対の安全はないという自覚を自分の意識の中に根づかせ、そのうえで彼我の状況(力関係)をたえず観察し、「構造」としての危険の可能性の認識を絶やさないという観点を、山に登るたびに考えてきた。それが事故防止の第一の策だと思われるからだ。 その1つの方法が、事故を自身の内でたえずイメージ化することではなかろうか。山岳会などグループで登山をするのであれば、自身たちの内で、と言い換えてもよい。それには、現実に起こった事故の状況を教材として脳裏に刻むこと、そして危険の潜む現場に接近したときには、危険を告げる信号を出す高感受装置を自身の中に常備すること、さらにそのイメージを引き出し、状況を「こわい」と思いながら通過する習慣を身につけることだ。そのように思っているが、1つの解でしかない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 本書は、具体的な事例、いわば「反面教師」としての教訓に満ちている。本書を通して事故の起こる経過がどういうものか、ということを「自身」の経験とダブらせて知ってもらい、事故防止意識の向上に少しでも役立ててほしいと思う。最後の結論として、「こわい」という気持ちをなくせば、事故の抑止はどこにもなくなるに違いないということである。「こわい」という気持ちが形だけのものだったなら、それは本物の抑止にはならない。本当に山を「こわい」と思う自身をどう形成し、構築することができるかではなかろうか、と近年考えるようになった。 なお、本多氏は故原眞先生のご友人で、銀座でお二人の山の絵画の展示会を催されたことがあった。それに、本会のメンバーと一度出向いたときに、本多氏に初めてお目にかかった。(2014/09/23 T・K) |
||